凡人の感想・ネタバレ>映画>グラン・トリノ
スポンサーリンク
執筆日:2018年5月16日
主人公のコワルスキーは妻に先立たれてしまった。二人の息子との繋がりも希薄なコワルスキーは孤独な晩年を過ごすだけの状況にあった。また周囲に住んでいるのはモン族という東南アジアの民族ばかりで白人のコワルスキーは孤立していた。だが、コワルスキーはある時モン族のギャングを追い返したことでモン族から敬意を払われるようになる。またモン族の少女スーはコワルスキーをモン族のパーティに招待するなどしたため、コワルスキーのモン族に対する警戒は徐々に解かれていった。スーの弟の少年タオがコワルスキーの愛車1972年式のグラン・トリノを盗もうとしたのがきっかけでタオと関わりを持つようになる。
車を盗もうとしたタオに対して償いとして庭仕事などをさせるコワルスキー。徐々にタオのことを気に入っていき、精神的に軟弱なタオを鍛えてやるなどしたのだった。
タオの従兄弟はギャングであり、度々タオに絡んではトラブルが起こっていた。コワルスキーはこれを仲裁してスーやタオを救ってやったりもするが、ついにギャングたちの報復でスーが暴行されてしまう。
激怒してギャングたちを殺そうとするタオ。しかしコワルスキーはそんなタオを一時的に檻に閉じ込めて「お前は誇れる友人だ」と言って一人でギャングの元へ向かう。
多数のギャングの前に現れたコワルスキー。しかしコワルスキーの思惑は「無抵抗でギャングに殺されてギャングたちを長期間刑務所送りにしてやる」ということだった。無数の弾丸を身に受けてコワルスキーは死んでしまった。
コワルスキーの葬儀が行われ、その遺書が読み上げられる。そこにはタオに対してグラン・トリノを譲るという内容が書かれていた。
タオはその通りにグラン・トリノを譲られ、それを運転して遠ざかっていくのがラストシーン。
コワルスキーは妻ドロシーに先立たれ、その葬儀が行われていた。だが出席したコワルスキーの孫たちは不真面目であり、2人の息子たちも頑固で古い価値観のコワルスキーに陰口を叩いていたのだった。
コワルスキーの孫のアシュリーはコワルスキーが大事にしている1972年式のグラン・トリノを見つけて気に入る。アシュリーは「おじいちゃんが死んだらどうなるの」などと聞くが、コワルスキーは冷たくあしらうだけだった。
また、神父のヤノビッチは妻ドロシーの知り合いで、生前のドロシーに「自分が死んだら気を使ってやって。懺悔に行かせてやって」と頼まれていたのだが、そんなヤノビッチに対しても冷たくあしらうだけだった。
妻を失ったコワルスキーはデトロイトにある自宅で愛犬のデイジーと共に孤独に余生を過ごすのみの状況となってしまった。しかもデトロイトにはアジア人がどんどん増えていき、今は自宅周辺には東南アジアのモン族という民族ばかりが住むようになっていた。モン族の老婆は「ここの白人はみんな出ていったのになんで出ていかない」などと愚痴をこぼしていた。
コワルスキーの家の隣に住んでいるモン族の少年タオは素行の悪いギャングの従兄弟を持ち、絡まれることもあった。そしてそのギャングはコワルスキーの家にあるグラン・トリノに目をつけたのだった。
再度ヤノビッチがコワルスキーの元を訪れる。
酒を飲みながら話をする二人。そこでコワルスキーはかつて朝鮮戦争に従事しており、人を殺した記憶に今も苛まれているということを神父に話したのだった。
ある夜、ガレージで音がしたので銃を持ってコワルスキーが見に行くとタオがグラン・トリノを盗もうとしていた。しかしタオには逃げられてしまう。
その後も再びギャングたちはタオの家を訪れてトラブルになる。タオの姉スーが騒ぎ立てていると、銃を構えたコワルスキーが現れ、銃で脅してギャングたちを退散させるのだった。
このことがあってから、周辺のタオ族の人間はコワルスキーに敬意を払って供え物を家の前に置くようになった。それを迷惑がるコワルスキーだが、これがきっかけでタオやスーと改めて挨拶をした。だがタオに対して「今度庭に入ったら命はない」などと言って脅すコワルスキー。
しかしその後、スーが黒人の不良に絡まれているのを偶然見かけてコワルスキーはそれも追い払う。
コワルスキーに善意は薄かったとはいえ二度も自分を助けてくれたことでスーはコワルスキーに好感を持つ。車の中で会話をして二人は親交を深める。
コワルスキーの元に長男のミッチとその妻が訪れて老人ホームのような場所で住むように提案するが、いらぬ気遣いに怒ったコワルスキーは息子夫婦を追い出してしまう。こうしてますます息子たちとは距離が離れてしまうのだった。
一方、スーからはバーベキューに来るように誘われたためにその誘いに乗るコワルスキー。
モン族の祈祷師がコワルスキーを見るというので頼むと、「人生に迷っている。過去の過ちから自分を許せない。幸せも安らぎもない」などと辛辣な分析をされてしまうのだった。
またバーベキューでタオが場になじめずに孤立しているのをコワルスキーは見ていた。ユアという少女とも知り合い、ユアがタオに気があるということを見抜いていたが、ユアを誘うこともできないタオを情けない意気地なしと容赦なく切り捨てるのだった。
そのタオが車を盗もうとした償いをしないと一族の恥だということで、タオはコワルスキーの言う事を聞くことになった。タオに庭の仕事や屋根の修理などをさせて親交を重ねるうち、コワルスキーはタオを気に入り始めるのだった。
実はコワルスキーは病に冒されていて、時折血を吐くこともあった。自分が長くないことを知ったコワルスキーはは長男のミッチに電話をするも、結局何も言えずに電話を切ってしまうのだった。
さらにタオの面倒を見てやって、床屋のマーティンとの荒っぽい会話を参考に男らしさを身に着けさせようとしたり、タオに仕事を紹介してやったりもするコワルスキー。タオは順調に男として成長していくのだが、再び従兄弟のギャングに絡まれてたばこを押し付けられて火傷をしてしまう。
これを知ったコワルスキーはギャングに銃をつきつけて「タオに手を出すな」と脅しを入れる。
その後、タオがユアを彼女にすることができたの知りコワルスキーは喜び、デートにはグラン・トリノを貸してやると約束もしてやるのだった。
だがギャングたちが報復としてタオの家に外から銃を乱射するという凶行を行う。
さらにその後、スーが血だらけで暴行を受けた姿で現れた。これを見たコワルスキーは茫然とし、自分がギャングを刺激したからだと後悔する。
タオは怒り狂い、ギャングたちを皆殺しにしようとする。コワルスキーはそんなタオを鎮める。
そして髪型を整えてスーツを仕立てた後にコワルスキーが行ったのはヤノビッチ神父への懺悔だった。
妻と結婚した後に別の女性にキスをしたこと、それに2人の息子との付き合いが分からず悩んでいたことをヤノビッチに懺悔したのだった。
そしてコワルスキーはタオに対してあたかも一緒に復讐をするような計画を話すが、タオを地下に閉じ込めた。そして朝鮮戦争で子供を殺したことが記憶に焼き付いていて今も夢に見るということを話し、「お前は大人になった。誇れる友達だ」と言って去る。
そして愛犬デイジーを隣の家に預けてギャングの元へと向かうのだった。
ギャングのアジトに現れたコワルスキー。ギャングたちを挑発し、銃を胸元から取り出す仕草をするが、取り出したのはライターだった。しかし銃を取り出すのだと勘違いしたギャングたちは一斉にコワルスキーに対して銃撃。あえなくコワルスキーは死んでしまうのだった。
この結果こそがコワルスキーが望んだものだった。非武装の人間を殺したということでギャングたちは長期間刑務所に入ることになり、タオ、スーたちの安全は保障されることとなった。
コワルスキーの葬儀が行われ、ヤノビッチ神父は「彼に生と死について教えられた」と皆の前で話した。
遺書が読まれた。
そこには大事に扱うならばグラン・トリノはタオに譲るという内容が書かれていた。
ラストはタオがグラン・トリノにデイジーを乗せ、海沿いを運転して走り抜けていくシーン。
世間ではかなり高評価なイーストウッド映画。
しかし自分が見終わった後には「う〜ん…」と唸るのみだった。もちろん、悪い意味で。
簡単に言えば「妻を失った頑固じいさんが隣に住んでいる情けない少年を気に入って心身ともに鍛え、最後には少年とその姉を守るためにギャングにわざと殺されてギャングを刑務所送りにする」という話だが、根底には「今時の若いもんは」という意識があるのだよなあ、この映画には。
つまり、朝鮮戦争で戦った自分は強くたくましいが、隣に住んでいるモン族のタオといい、その従兄弟のギャングといい、情けないし軟弱だ!みたいな。年老いた主人公より若者たち(タオにせよギャングらにせよ)は精神的に劣っているということが前提で成り立つ物語だ。そしてそれが作中で特に否定されることはない。ここが若干気持ちが悪い。
そしてコワルスキーは自分の息子や孫に対しても愛情は薄く、最終的にはタオに大事にしていたグラントリノをも譲るわけだが、この息子や孫に何の救済もないのがちょっとあんまりじゃないか?と思えるのだ。
つまり、コワルスキーとその親族の関係が冒頭の葬儀シーンから何ら変わらないで終わってしまったということ。自分が引っかかった点は結局、ここなのかもしれない。
無論、タオというモン族の若者とのかかわりを通してコワルスキーは孤独を埋め、またタオもコワルスキーに影響を受けて精神的に強くなるという筋書自体には文句はない。
だが、むしろコワルスキー目線から見て、死ぬ前に自分の息子や孫との確執がいくらかでも解消できていないのはどうにも悲しくないだろうか?
コワルスキーの死後に読み上げられた遺書。そこに書かれていたのはグラントリノをタオに譲るという内容。そしてそれを聞いて落胆する孫のアシュリー。視聴者としてはここでアシュリーに「ざまあみろ」と思えるだろうか?少なくとも自分は思えなかった。むしろ「コワルスキーは孫に死を悲しまれるどころか愛車の行方がどうなるかを気にされるだけなのだなあ」となんとも悲しくなってしまった。グラントリノを譲られたタオはもちろん、今後人生を強く生きていくのだろう。だがコワルスキーの親族たちはどうか?「血のつながりもないアジア人に高価なものを譲り渡した最後までいけすかないクソじじい」と思い続けるだけに違いない。コワルスキーは頑固で強情なところは最後まで変わらず、そのおかげで家族からも疎まれていたわけだが、ここにコワルスキーに全く非がないと言えるだろうか?もちろん、ないわけはないのだ。だが、先に書いたようにこの作品はコワルスキーが頑固で強情な厄介な年寄りであるところが否定されることはない。
一言でまとめると、タオとの繋がりを通してコワルスキーの性格も軟化し、親族との関係も修復するエピソードが入っていればよかったなあと思ったわけだ。ラストは同じにしても、それだけで視聴後の印象は全然変わったろうになあ。家族からただ疎まれるだけのじいさんで終わってしまっては、いかに息子や孫に代わるタオ、スーという存在を死ぬ前に得ていたとしても、感動ストーリーというよりはむしろ悲しい話に思えてしまってならない。そりが合わないとはいえ唯一無二である家族たちをただ悪役に据えなくてもいいんじゃないか?ってことだ。何のためにいるのかよくわからない神父を登場させるよりはそっちに重きを置いてほしかった。医者へ行き診断を見て自分が長くないと知ったコワルスキーがミッチに電話したシーンでは「ここから家族仲も修復するのか」と思ったんだけどなあ。孫のアシュリーなんかは性格悪いが、ミッチに関してはできればコワルスキーと仲良くしたがっているような節もあったので、なおさら家族仲に関しては何の変化がなかったのが拍子抜けというか残念というか。
あとラストでギャングたちに集中砲火されて撃たれるシーンだが、イーストウッドって多数の悪党に対して一人で立ち向かうの好きだなあと。これは「ダーティハリー」だったり「許されざる者」だったりを見ていると思ってしまうことだ。
この作品グラントリノはそういうアクション映画や西部劇とは違う。ヒューマンドラマだ。「こういう作品でも妙に格好いいシーン入れたいのか」なんて皮肉った目で見てしまってどうも。すでに10年以上前の作品だが、この時すでにイーストウッドは80手前、もういい年なんだから西部劇のガンマン気取るのはやめようよ、なんて感じた。
ただこれって、イーストウッドにとってはセルフオマージュみたいなものなんだろうな。あのイーストウッドが懐に手を入れたら取り出すのは…!というパブリックイメージを利用しているのだろうと。だがそう理解しても、この作品では別に西部劇を思わせる演出を入れる必要はなかったと思うには変わらないかな。自己満足のように感じてしまう演出だった。
演:クリント・イーストウッド
デトロイトに住み、アメリカの自動車会社フォードに50年務めた男性。愛車1972年製グラン・トリノを大事にしている。妻に先立たれ、子供二人や孫からも疎まれて孤独になりつつあったが、隣に住んでいたアジアのモン族の姉弟、スーとタオと出会って心を通わせ、2人を実の子供あるいは孫のように思うように。そしてギャングの手から守るためにわざとギャングたちに銃殺されるように誘導。遺書にはタオに愛車グラン・トリノを譲る旨が書いてあった。
演:ビー・ヴァン
コワルスキーの家の隣に住んでいる東南アジアの民族のモン族の少年。優しい心を持つが男性としての強さに欠けていて、ギャングの従兄弟にコワルスキーのグラントリノを盗むように命令されて盗難未遂に。それを見逃された代わりにコワルスキーの言う通りの仕事をして、次第にコワルスキーと親しくなる。姉のスーがギャングに襲われたことで皆殺しにしようと激昂するが、コワルスキーの家に閉じ込められてしまい、コワルスキーが一人でギャングの元へ向かうのをただ見送ることしかできなかった。コワルスキーの死後、遺言書にあった通りグラン・トリノを譲り受けた。
演:アーニー・ハー
タオの姉。孤独なコワルスキーと仲良くなり、コワルスキーがタオはじめモン族と親しくなるきっかけとなった少女。強気だが優しい性格。しかしギャングたちに暴行されてしまう。
演:クリストファー・カーリー
コワルスキーの妻の知り合いで、その頼みでコワルスキーの世話を焼こうとする神父。しかし人を寄せ付けようとしないコワルスキーからは一蹴されてしまう。しかししつこくコワルスキーにまとわりつくうちにコワルスキーも神父に気を許すようになっていった。
演:ジョン・キャロル・リンチ
コワルスキーが贔屓にしている床屋の主人。傍から見るとコワルスキーとマーティンは酷く罵り合っているようだが、それは心を許している間柄でこその会話。コワルスキーはマーティンとの会話を参考にタオに男らしさを身に着けさせようとした。
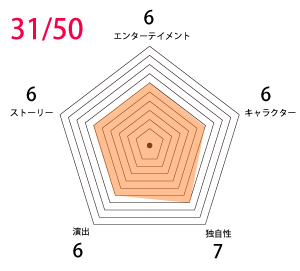
自己犠牲によるラストシーンで感涙する話、なのかもしれないが、さほど心に沁みるものはなかった。タオ、スーらモン族と仲良くなったのはいいが家族仲は最悪のままにコワルスキーが死んでしまったのがなんかいたたまれない。他のイーストウッド作品を見てると撃たれるシーンで「こういうの好きだなあ」なんて冷めた目にもなってしまうのがどうにも。アクション映画ではなくヒューマンドラマなのだから変にダーティハリーぶって格好つけることはなかったと思う。
凡人の感想・ネタバレ>映画>グラン・トリノ